--ヒートアップする塩ブーム多種多様な中から最適な塩を探し出そう-- |
||
|
|
||
|
中世後半からは、潮の干満差を利用して海水を塩田に引き込む「入り浜式塩田」(イラスト2)が登場する。潮汲みの労働が軽減された入り浜式は、江戸時代から盛んに取り入れられるようになり、海岸に近い藩はこぞって製塩に力を入れた。塩は戦国時代の大切な兵糧であり、武具に使う毛皮をなめす材料としても不可欠。 平釜の材質や煎ごう技術も発達し、赤穂流といわれる立体式の画期的なかまどが出現したのもこのころである。入り浜式で塩が作られていた時代は約300年と長く、昭和27年ごろまで続いている。 昭和20年代に入ると、傾斜をつけた流下盤と粗朶や竹を吊るした枝条架で塩分を濃縮、乾燥させる「流下式枝条架式塩田」(イラスト3)に取って変わるようになる。この方法は太陽熱と風による蒸発が効果的に得られる上、24時間体制の操業が可能。従来の10分の1の労働力で3倍の生産量を上げることができた。流下式は主に瀬戸内地方で発達した。 |
||
 |
||||||||
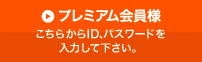  |
||||||||
| Copyright(C) FOODRINK CO.,LTD All Rights Reserved |